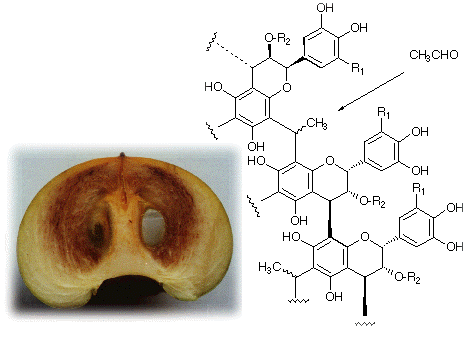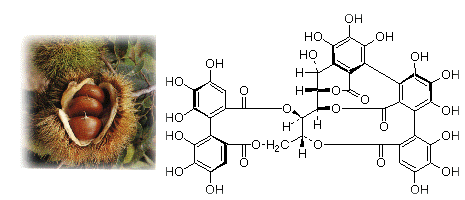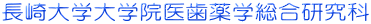
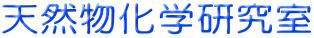
タンニンについて
1. 柿の渋抜き
種子を守るためのタンニン
渋柿を食べたことありますか。あの強烈な渋味のもとがタンニンです。柿は種子が未熟な間、多量のタンニンで守っています。しかし、種子が充分成長したら種子を遠くに運びたい。日の当たらない親の根本では子供は育ちません。だから熟柿になると人やカラスに食べてもらえるように軟らかくなり、渋味がなくなります。
渋柿を風呂に一晩つけたり、焼酎(エタノール)や二酸化炭素で処理すると人工的に渋抜きすることができます。渋が無くなるのではなく、水に溶けなくなるために渋味を感じなくなります。これはいずれの処理でも嫌気的呼吸によりアセトアルデヒドができて、それがタンニンを重合させるために起こります。甘柿はもともとタンニンが少ない種類を人間が選抜したものです。
T. Tanaka, R. Takahashi, I. Kouno and G. Nonaka, Chemical Evidence for
the De-astringency (Insolubilization of Tannins) of Persimmon Fruit. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 3013-3022 (1994)
2. クリ材部のタンニン
木材における細胞の死と防御物質としてのタンニン
クリは果実を食用にするので広く栽培されますが、その木材は非常に耐久性が強いことから建築土木資材としても重要なものです。その耐久性はタンニンを含んでいることによると言われています。タンニンにはカビなどを防ぐ効果があります。
木材の細胞は樹が太くなるにつれ内側に取り残され、ついには樹皮からの栄養の供給がとだえて、すべて死んでしまいます。細胞は死ぬまぎわに最後の力をふりしぼり、大量のタンニンを作ります。大樹を支える樹の中心部はこうやってカビから守られます。
タンニンがあると普通カビは生えませんが、シイタケ菌はタンニンを分解する能力を持っていて、木材のセルロースを栄養源として成長します。他のカビが利用できない資源をシイタケは独占できるのです。
ちなみに、クリの渋皮のタンニンは樹皮や材のものとは全く違う構造をしており、柿のものと似ています。多くの植物が組織によって作り分けをしていますが,理由はまだ分かっていません。
T. Tanaka, N. Ueda, H. Shinohara, G. Nonaka, T. Fujioka, K. Mihashi and
I. Kouno, Four New C-Glycosidic Ellagitannins, Castacrenins D-G,from Japanese
Chestnut Wood (Castanea crenata Sieb. et Zucc.). Chem. Pharm. Bull., 45, 1751-1755 (1997).
T. Tanaka, N. Ueda, H. Shinohara, G.-i. Nonaka, T. Fujioka, K. Mihashi
and I. Kouno, C-Glycosidic Ellagitannin Metabolites in the Heartwood of
Japanese Chestnut Tree (Castanea crenata Sieb. et Zucc.). Chem. Pharm. Bull., 44, 2236-2242 (1996).
戻る